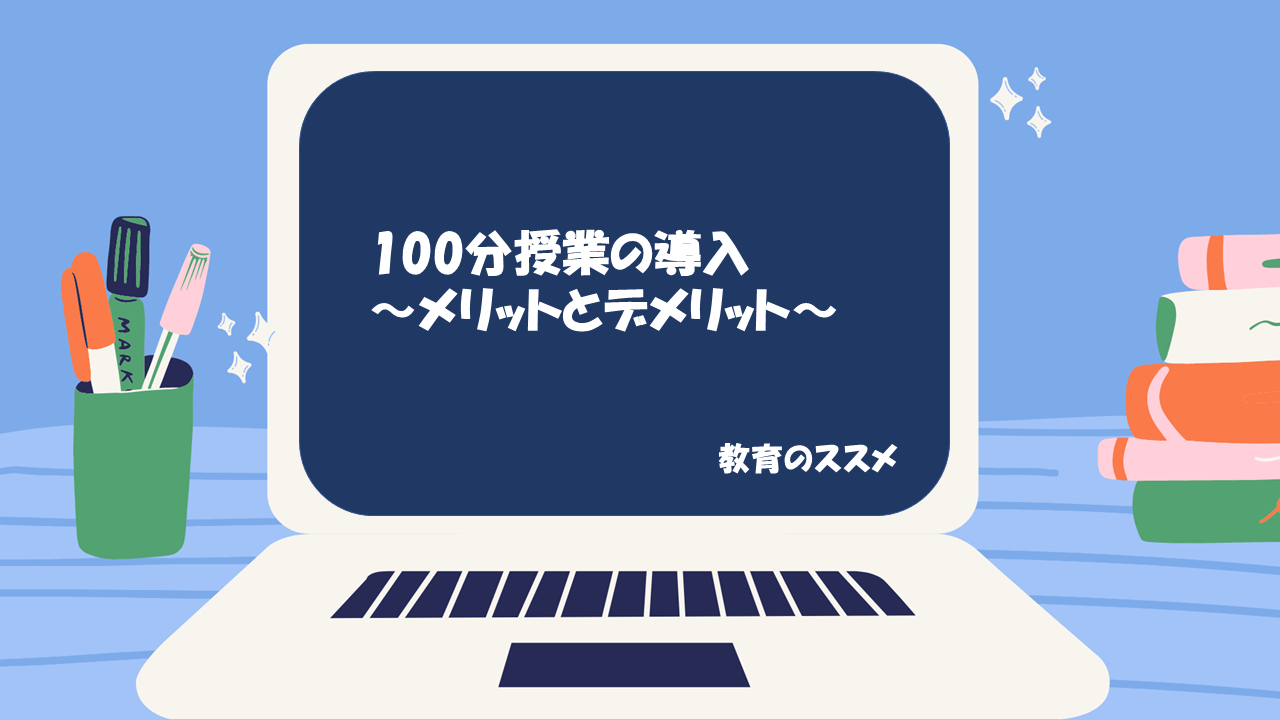今回は、100分授業について紹介します。
100分授業の導入の背景について
大学の単位設置条件については、大学設置基準というもので決まっています。
従来、90分15週の講義で2単位が付与されるという決まりがありました。
また、定期試験についてはこの時間に含めて良いかは必ずしも明確ではありませんでした。
一方で、平成20年の中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」においては、単位の実質化を重視する観点から、定期試験期間については、授業時間数には含めない。
というような記述が示されました。
このような状況から、『90分15週+定期試験』という学事暦を設定するためには、春学期が8月まで伸びる状況や、秋学期では、2月の入試時期まで授業期間を設けることが問題となっていました。
他にも、認証評価機関(大学が正しく運営をされているかをチェックする機関)による評価は、しっかりと、『90分15週+定期試験』が確保されているか。
という点が評価対象となっていましたが、議論の結果、
単位の実質化・学修時間の実質化という観点から考えると逆行するのではないか。という結論になりました。
この結果、大学設置基準第23条が、
各授業科目の授業期間”>第二十三条 各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとするただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
という文言に変更されました。
これにより、従来90分15週で行われてきた授業(集中授業等は除く)が、弾力的な運用が可能となりました。
つまり、
90分×15週=1350分を合計で確保できれば良く、100分×14週=1400分(1350分で良いため、残りの50分は補講等の予備時間)での実施が可能となりました。
100分授業導入大学はどこ?
この柔軟な授業期間の設定により、既にいくつかの大学で100分×14週で実施している大学があります。
具体的には、
※2024年度実施予定大学まで確認できた範囲で更新しました。
※2022年度から105分授業を導入する大学も記載しています。
2015年度から
東京大学(105分授業)
2017年度から
明治大学、芝浦工業大学、静岡産業大学
2018年度から
法政大学、神奈川大学、京都外国語大学、大阪工業大学、成城大学、東京電機大学、東海大学
2019年度から
上智大学、立教大学、日本女子大学、獨協大学、桜美林大学、岩手大学、島根大学、中央大学
2020年度から
九州産業大学、横浜商科大学、東京女子体育大学、東京工科大学、成蹊大学、聖心女子大学、広島工業大学
2021年度から
実践女子大学、京都橘大学、関西学院大学、南山大学、武蔵野大学
2022年度から
麗澤大学、拓殖大学(105分授業)、武蔵大学(105分授業)
2023年度から
早稲田大学、城西大学(105分授業)
2024年度から
学習院大学、茨城大学(105分授業)
となります。
大学の一覧を見ると、上智大学、MARCHの大多数、更には国立大学までもこの100分授業を導入しています。
2020年度以降の動きを見てもわかるようにこの学事暦の弾力化は、各大学にとって非常に魅力的なもののようです。
 たろう
たろう2017年度から変更した、明治大学、芝浦工業大学、静岡産業大学この3つの大学は教育改革が非常に進んでいるのかもしれません。
2023年度からついに早稲田大学も導入することになりました。
100分授業導入の意見は?
今までの90分15週の授業から、100分14週になったことで、
学生や教員はどう感じているでしょうか。
やはりメリットとデメリットの両方の側面がありそうです。
【肯定的な意見】
 Bさん
Bさん集中して授業を行うので、授業の理解が深まった
 Cさん
Cさん休日授業が減ったため、まとまった休みがとれる
時間が長いため、余裕を持った授業展開ができる
【否定的な意見】
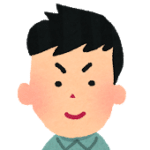 Cくん
Cくん帰る時間が遅くなった
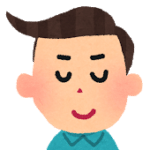 Bくん
Bくん100分なんて座っていられない
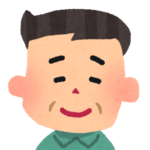 B先生
B先生集中力がもたない。学生が途中で飽きてしまう
確かに90分でも集中して授業を聞くと長かったのに、100分なんてなおさらキツい!
という人は多いと思います。
また、終了時間が遅くなることで、バイトがサークル活動に支障がでているケースが少なくありません。
ただ、14週で終わることで、夏休みが早く始まったり、冬休みが早く始まったりと、メリットとなる部分もあるので、今後も導入する大学は増えてくるかもしれません
そもそも100分も必要?昔は適当だったような…
大学で学んだことがある方からすれば、
そもそも学生時代って、90分で14回しかやらなかったり、突然休講になったりと、
あんまり厳密にやっていなかったのでは?
と感じる方もいるかもしれません。
そうしたある意味でいい加減だった授業時間をしっかりと確保しようという流れから、このような体制になりました。
学生からしてみても、せっかく高い学費を払って大学に通っているので、突然休講になったり、決められた時間数が設けられなかったりしたら迷惑ですよね。
学生からすれば、休講になるだけで嬉しく、友達と遊びにいってしまうかもしれませんが、勉強をみっちりできる期間も大学を卒業するまでなので、頑張って100分14週を乗り切りましょう!
いかがでしたでしょうか。
今回は100分授業について紹介してきました。
もうひとふんばりと思ったら個別指導塾の検討はいかがでしょうか。
東京個別指導学院なら、授業は1対1または1対2の完全個別指導で、担当講師も相談のうえ決定されます。
また、1人ひとりに合わせたオーダーメイドカリキュラムだから、苦手な科目も丁寧にフォロー!
まずは無料の資料請求から!
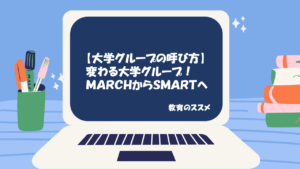
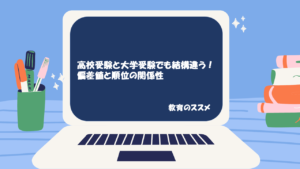
各大学に特化した対策で1日単位で徹底管理してくれる。
 たろう
たろう各大学特化のカリキュラムに興味がある方はこちらもどうぞ。